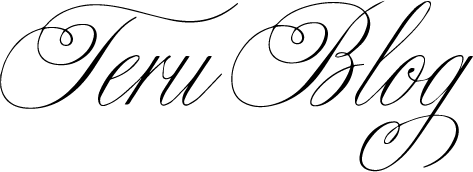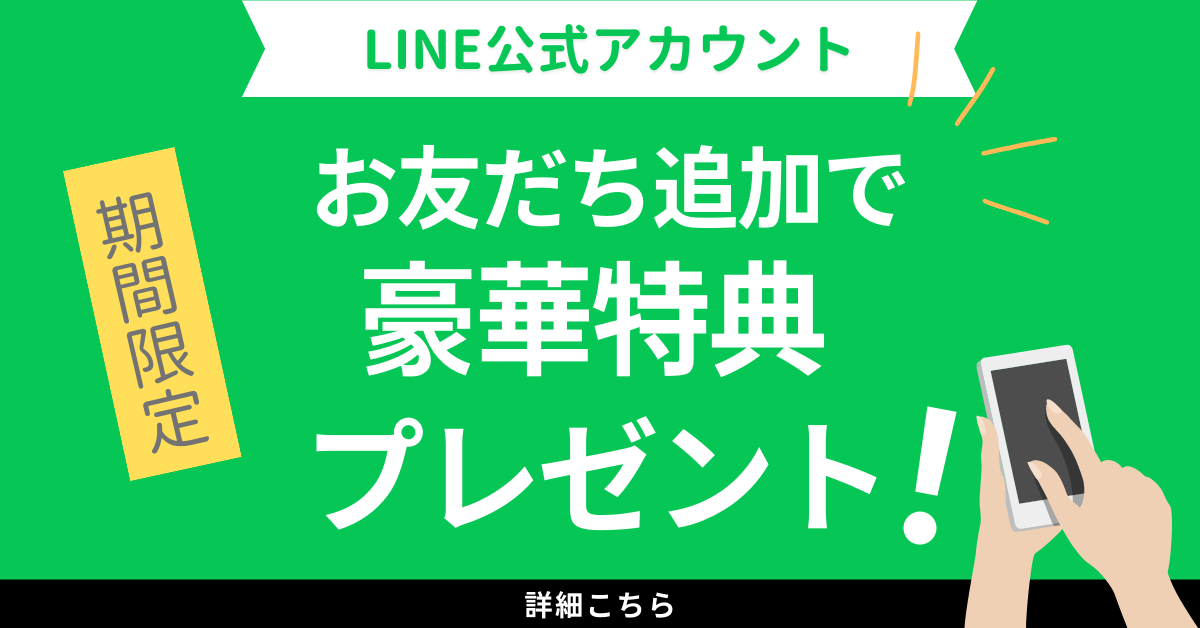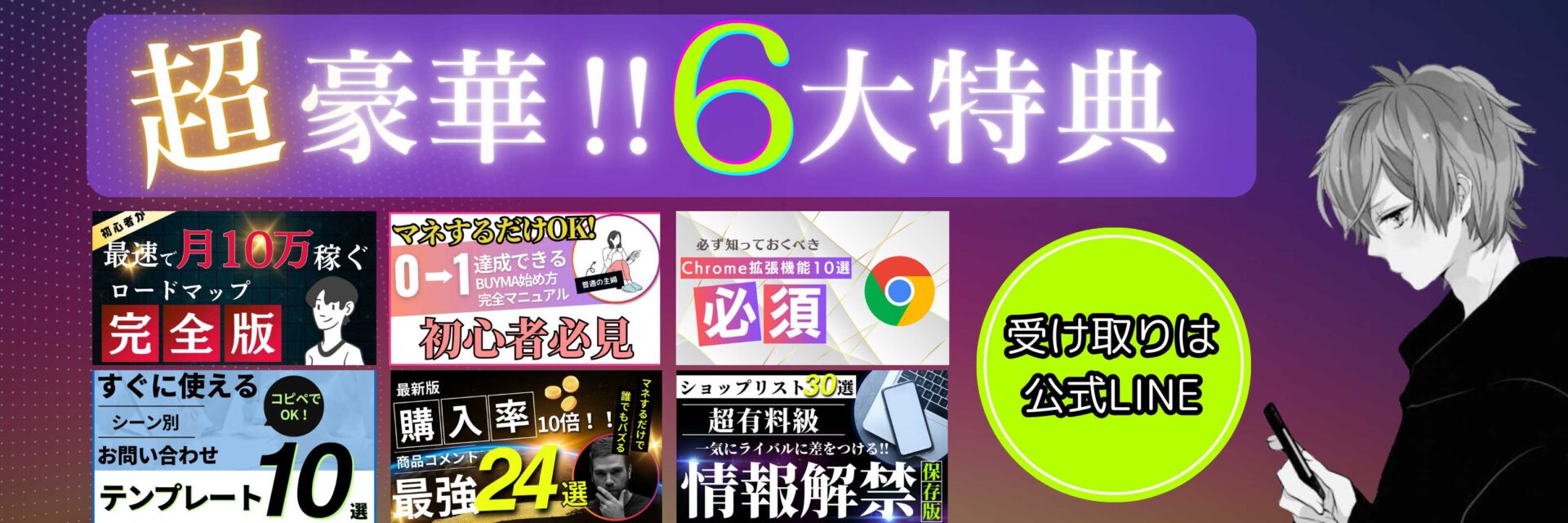成果を出すために大切なことは、既に成果を出している人の真似をすること!
皆様は日ごろ【結果】や【成果】を出すためにどのような努力をされていますか?
【結果】や【成果】を出すというのは《何に対して》なのかによってプロセスは異なります。
しかし、基本的に目標が違っても歩むべきプロセスは共通するものが多くあるように思います。
ただやみくもに真似をしてもうまくいく可能性は非常に低くなってしまいます。
ではどのように真似すればいいのでしょうか。
読んでよかったと思える記事になっていますので是非最後まで読んでくださいね。
大切なお知らせ
公式LINEのお友だち追加はこちら↓↓
目次
野球少年がイチロー選手の真似をしてみたけれどうまくいかなかった。
野球をしている人たちの憧れの的はイチロー選手!!と言っても過言ではないほどイチロー選手は世界を代表するプレーヤーです。
その華やかなスーパースターの裏で並々ならぬ努力をされていたこともよく知られています。
もちろん天性の才能があったことに疑う余地はありませんが、日々、努力しているからこそ誰もたどり着けない境地に至ることができたのだと思います。
そんなイチロー選手に憧れ、バッティングがうまくなりたいと思ったらイチロー選手のバッティングを真似てみようと思った方も少なくないはずです。
しかし、ただ真似するだけでイチロー選手と同等のバッティングができるようになってしまっては世の中凄腕のバッターばかりになってしまいます。
なぜだめだったのでしょうか。理由を検証していきたいと思います。
【結果】や【成果】を出すために『やり方』を真似するだけではなぜうまくいかないのか。
イチロー選手の打ち方を研究し、形としては瓜二つというくらい真似できていたにも関わらず、成果を出すことができなかった。
その理由は、イチロー選手自身がご自分のやり方の中で創意工夫されていたからです。
これはイチロー選手の本などを読んでいただくと書いてあったりするのですが、その創意工夫のやり方こそがとても参考になります。
どんな風に創意工夫すればいいのでしょうか。いくつかご紹介したいと思います。
自分でコントロールできるものに最善の注意を払う
ヒットを何本打つかというのはイチロー選手であってもコントロールするのは難しいと思いますが、バッターボックスに入るときのコンディションというのは自己管理することができます。
食事だったり睡眠だったり、気持ちの持って行き方だったり自分でコントロール可能なものに注意を払うことで、バッターボックスに入るときのコンディションを最高潮に持って行くことができ、ベストコンディションで試合に臨むことができるというわけです。
もうお気づきの方もいるかもしれませんが、多くの方は『自分でコントロールできないもの』に対して最善の注意を払い、目を向けがちです。
しかし実際の試合となれば、天候や相手のピッチャーとの相性、芝のコンディションなど、自分ではコントロールできないものもたくさんあります。
その中で自分がコントロールできるものをきっちりと認識し、徹底してコントロールすることが大切であり、そのコントロールの結果、野球界でのスーパースターになるという偉業を成し遂げているわけです。
日々のルーティーンワークは慎重かつ大切に
ルーティーンワークと聞いて何を思い浮かべるでしょうか。
社会人の方であれば、毎朝メールをチェックするなどは日々のルーティーンワークですよね。
このルーティーンワークには新鮮さもありませんし、正直あまり楽しくないイメージを持たれている方が多いと思います。
しかし、イチロー選手においてはこのルーティーンワークをとても重要視されています。
毎日同じ時間に同じ場所で同じことを繰り返すことを何十年もずっと続けているそうです。
朝起きて、球場へ移動するまで、球場についてからウォーミングアップをし、試合が始まるまで、試合が始まってからバッターボックスに立つまで、試合が終わってから帰宅するまで。
これは試合がある日の例ですが、この流れが分単位できっちり決められていて、ルーティーンワークとしてこなします。
野球はあまり見ないといった人でもイチロー選手がバッターボックスに入ったとき、袖を引っ張りながらバットの先端を投手側のバックスクリーン方向へ向けるという行動を見たことがある人は多いと思います。
野球が好き、イチロー選手が好きといった方は、もう数えきれないほどこのしぐさを見ていると思います。
そして、熱烈のファンの方であればご存知かもしれませんが、イチロー選手はネクストバッターズサークルの中で毎回同じ動きをしています。違った動きや無駄な動きは一切していないんです。
試合がオフの日やシーズンオフの日などはまた別のルーティーンワークがあると思いますが、こちらも分単位できっちり決められていてそれに則って行動しています。
そこまで細かく決めなければならないのか?イチロー選手はなぜそこまで細かく決めているのか?
それは『自分自身の中での違和感を感じとるため』だそうです。
毎日毎日同じことを繰り返すことで、多少の違いも感じ取ることができます。
これはフィジカル面もメンタル面も同様で、少しでも違和感を感じとることができるようになる、すなわち『危機管理能力』が非常に高まるということでした。
こういった違和感を感じとるためのルーティーンワークをしていると、違和感がないと実感できたときに、自分の中で大きな自信につながり、今日は大丈夫だと自分に対して言い聞かすことができます。
逆におかしいなと思えば、何が違うのだろうと考えることができ、自分自身をコントロールしやすくなります。
違和感の原因を探り当てることができれば、修正することができるため、そこからベストに近いコンディションに持って行くこともできます。
その結果、安定して高打率などの結果を生み出すことになったということです。
やれることは可能な限りすべてこなす
先述通り、イチロー選手は試合前の準備は徹底的に納得がいくまできっちりとこなします。
イチロー選手は、結果が出せなかったときに言い訳できる要素を残して試合に出ることをしたくない。
そのために準備は抜かりなく行うのだそうです。
基本的に人というのは何かうまくいかなかったときにうまくいかなかった原因は何なんだろうという原因を探ります。
原因を見つけたはいいですが、その原因の中に自分が努力しなかったこと、さぼってしまったことなど自分に非があることがあれば、その事実から目を逸らそうとします。
これは人であればほとんどの方がそうであると思うので、決して間違っているというわけではありません。
しかし、イチロー選手はうまくいかなかった本当の原因は何なんだということをきっちり見分けることが重要だと考えています。
そのため言い訳できる要素をすべて排除することに重きを置き、試合前に徹底的に準備するというスタンスはなかなか貫けるものではありません。
野球選手としてはもちろんですが、人としてもとても尊敬に値する人だなとつくづく思います。
【結果】や【成果】をあげるために最も重要なことは、やり方を変えるのではなく、在り方を変えてみること
イチロー選手はやり方にこだわっているのではなく、むしろ在り方を重要視しているということがよくわかっていただけたかと思います。
バッティングフォームやボールの投げ方などはあくまでもやり方。
言ってしまえば表面的なテクニックです。
もちろんイチロー選手は表面的なテクニックに関しても抜かりなくトレーニングされています。
しかし、その表面的なテクニックの前に自分自身の在り方をきっちりと確立され、徹底的に鍛えているということがよくわかりました。
人は憧れを抱いた時にその人のやり方だけを見てしまいがちです。そしてそんな風になりたいと思い、やり方を真似します。
しかしやり方だけを単純に真似すればその人のようになれるということであれば苦労などありません。
【結果】や【成果】というのはそんなに簡単に生まれるものではないということです。
まとめ
いかがでしたか?
今回はわかりやすく野球に例えて書かせていただきましたが、これは会社の中でもそうですし、人生の中での成果を求められるすべての場面で同じことが言えると思います。
まとめると、
【この考え方の本当の意味が分かるのはあらゆる場面で成果を求められたとき】
です。
例えば営業職の人が社内で成績を残している先輩に憧れてやり方を真似してもなかなかその先輩のように成績が上がらなかったりするのはそのせいだったりします。
テクニックばかり盗もうとして、日々の努力やその人のスタンスを理解できていなければうまくいくわけありません。
どのようなスタンスで仕事をしていて、どのようなプロセスを経て結果につながっているかということから学ぶ必要があります。
【結果】や【成果】を出すためには、何をどのように考えてどのように行動し、今までの自分をどのように変えるべきなのかという自分自身の在り方を見つめなおす必要があります。
成績を残している先輩の在り方と自分の在り方を比較することでどうしたらいいのかということはおのずと見えてくるはずです。
【結果】や【成果】を出すということは決して簡単ではありません。
あの人は才能があるから!などということを聞いたりしますが、たとえ才能があったとしてもそう見えているだけで、陰では並々ならぬ努力をされていることと思います。
上記内容にも記載しましたが、是非努力をする中にルーティーンワークをぜひ取り入れてみてください。
ルーティーンワークを取り入れるメリットはたくさんあります。
ビジネスにおけるルーティンワーク
ここまでできるようになると、ビジネス面ではルーティーンワークを実施しして【結果】【成果】が出たと言えます。
スポーツにおけるルーティンワーク
以上のことから、ルーティーンワークはとても大切ということがいえます。